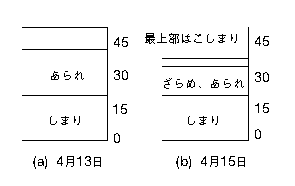
本稿では、まず我々がザトルワラで停滞を強いられた雪崩について 報告する。次に登山隊の講じた雪崩対策をもとに、ヒマラヤ登山で 可能な雪崩対策について考えてみたい。
ルクラの南東約5kmに位置するザトルワラ(標高4600m)北西斜面は、 雪崩の多発地点として知られている。ザトルワラで積雪断面観測を 行なったところ、表層下にある厚さ25cmのあられ層を観測した。観測後 9時間以内に、断面観測地点を含む沢型で、あられ層を滑り層とした 表層雪崩が発生したのでその概要を報告する。術語等については 参考文献1を参照されたい。
| 日時 | 観測地点の標高 | 天気概況 |
| 〜4月7日午前 | 3400m | 晴れ、融雪が盛んに起こる。カル カテンでは沢中に積雪がほとんど なくなったことが観測された。 |
| 7日午後〜8日午前 | 2800m | くもり |
| 8日午後〜10日 | 2800m 3400m |
みぞれ混じりの雨 |
| 11、12日 | 4050m | あられと湿雪が交互に降る |
| 13日 | 4050m | 湿雪、夕方に雪崩頻発 |
| 14、15日 | 4050m | 強い日射のため10時ごろからガスが かかるが、夕方には晴れる。夜は 快晴。昼間雪崩頻発。 |
天気概況を表1に示す。断面観測は、4月13日午前6時と15日午前 8時にカルカテン(標高4050m)の沢型で行なった。断面観測結果を 図1に示す。また断面観測と共に積雪層のせん断強度を知るために 弱層テストを実施した。雪崩は4月13日の夕方から断続的に発生した。
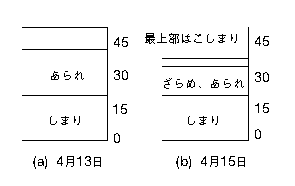
この期間にルクラ(2800m)やチュタンガ(3400m)で観測した 気温を、断面観測を実施したカルカテンでの気温に換算すると、 カルカテンにおけるいずれの日の気温も約0℃であった。換算には 湿潤断熱気温減率 6℃/km を用いた。また4月6日には、一部の 沢底に氷化した雪が残っている他は地面が露出していることが 観測された。このことから、断面観測時に観測された積雪底面付近の 氷板としまり雪は、それぞれ4月6日以前と6〜10日に形成された と考えられる。
13日の断面観測では、あられ粒子同士の結合が極めて脆くピットが 掘れない状態であった。また弱層テストを実施するとあられ層の 内部で簡単に破断した。断面観測後9時間以内に断面観測地点を 雪崩が通過した。
15日は、あられがざらめ化しブロック状になり結合が発達していた。 また弱層テストを実施するとブロック状に破断した。断面観測地点は 沢型の下部で斜面が十分ゆるいため雪崩は通過しなかったが、 観測時には観測地点の約20m上方までデブリが堆積していた。
(a) 滑り層の推定
今回の事例では、雪崩発生直前の断面観測においてあられ層が顕著な
弱層となっていたこと、断面観測直後に雪崩が観測地点を含む沢型で
発生したことから、あられが滑り層となったと考えてよい。一般に
あられが滑り層となり得るということは知られているが、実際に
そのような雪崩を観測した事例は少ない。
(b) 雪崩発生機構の推定
13日の断面観測結果によると、あられ粒子間の結合はほとんど発達して
おらず、あられ層は粒子間の焼結が進みにくい条件下(すなわち低温)に
あったと考えられる。また15日の断面観測結果によると、あられ層内に
ブロック状の結合が発達している。13日にほとんど焼結していない粒子が
観測されたことから、この結合は48時間程度の間に起こったものである。
14日は非常に日射が強く、あられ層上部の温度が0℃に達していたと
考えられる。そのため日射や層上部の融解水の流下によって融解が進み、
その後夜間に気温が下がり、あられ層内にトラップされていた融解水が
凍結することによってブロック状の結合が発達したと思われる。
13日に観測されたあられは、直径1mm程度で非常に転がりやすいもので あった。そのため、降雪後のあられは斜面を転がり、重力に対して 安定な位置で堆積したと考えられる。したがってこの状態では雪崩は 発生せず、観測された雪崩は積雪内部の融解を伴う現象をトリガー として発生したと考えられる。
13日に観測された25cmの積雪層は、48時間後の15日には18cmにまで 圧縮された。すでに重力作用によって充填されたあられ粒子が更に 充填されたのは、融解を伴う粒子の変形が寄与したものと考えられる。 融解水があられ粒子同士の摩擦を減少させたとも考えられるが、 7cmもの積雪層の圧縮が観測されていることから、前者の機構が雪崩 発生の支配的要因となったと考えられる。
山森の報告によると、日本人のヒマラヤにおける遭難の49%が雪崩に よるものである。すなわち、雪崩遭難がなくなれば、遭難は半減する。 そのため、雪崩遭難に対する具体的対策が強く望まれる。
今遠征の派遣母体である北大山とスキーの会及び山スキー部では、 日本で初めて雪崩ビーコンをクラブとして導入するなど、雪崩対策に 関して非常に積極的なクラブである。今遠征でとられた雪崩対策に ついて述べると共に、ヒマラヤにおける雪崩対策について少し述べたい。
今遠征中の雪崩対策として実施したことを以下に列挙する:
1)過去の雪崩遭難の情報収集及びケーススタディー
2)雪崩地図の作成
3)弱層テストの励行
4)雪崩ビーコン、ゾンデストックの携行。
1)、2)を行なうことによって危険地帯を明らかにすると共に、3)に よって雪崩発生の判断を科学的な根拠にもとずいて行ない、4)を 行なうことによってセルフレスキューを可能にした。
1)は文献2,3をもとに行なった。情報収集は重要であるが、過去に 雪崩が発生していないから安全と考えるのではなく、過去に雪崩が 発生しているから危険と考えるべきである。登山隊によってもたら される雪崩発生の情報は、空間的にも時間的にも限定されたものであり、 それだけから安全と判断するのは危険である。
2)は信頼できる地図が入手できる場合に有効な方法である。高橋の 導いた経験則によると、表層雪崩の場合は斜度が18°以上の場所が、 全層雪崩の場合は25°以上の場所が雪崩の流路となり得る。しかし、 一般に登山ルートで18°以上の部分にゾーニングを行なうとほとんどの 地域が危険地帯となり、実用上意味がない。今回は登山ルートに面した 斜面の斜度を地図の等高線の間隔から割り出し、25°以上の部分を 危険地帯と判断した。
3)は登山者が雪崩発生の危険性を科学的に推測することを可能に する簡易な方法である。直径30cm(一抱え程度)、深さ70cm以上の積雪の ピット(円柱)を作る。そしてそのピットを抱きかかえて手前に引っ張る ことによって積雪層に(雪崩発生時にかかる)斜面上方から力を加え、 積雪層の強さを判定する方法である。この方法を用いることによって、 従来カンに頼っていた雪崩の危険性を、ある程度客観的に評価できる。
4)はパーティーによるセルフレスキューを可能にする方法である。 ビーコンとは電波送受信機で、遭難者の所持するビーコンの発する電波を 捜索者のビーコンで受信し、遭難者の位置を特定する方法である(例えば、 文献4に詳述)。この方法によると、捜索開始後5分程度で遭難者の 位置を特定することができる。次に遭難者を掘り出すが、体力を消耗する 掘りだし作業を迅速に進めるために、高所ではゾンデが必要であろう。 スイスやアメリカにおける雪崩遭難に関する幾つかの統計資料(例えば、 文献5)によると、30分以内に掘り出された遭難者の生存率は50%で、 生存率は時間とともに指数関数的に減少する。なお、酸素の薄い高所では、 時間に対する生存率は統計資料のそれより小さくなると思われる。
登りたいという強い気持ちを持てば持つほど、危険に対する配慮は行ない にくくなる。特にヒマラヤ登山の場合は、「せっかくここまで来て...」と いう心理もあり、危険な登山を強行する可能性が高い。そこで、より 合理的な判断を行なうことを助ける客観的根拠が必要である。準備段階 から雪崩の危険性を隊員に周知させるためにも、登山ルートの選定を 容易にするためにも、雪崩地図は有効であろう。また弱層テストを自分の 手で行ない、危険性を判断する機会を持つことは、冷静な判断を可能に してくれる。
雪崩地図の示す危険地帯を完全に避けて登山することは不可能である。 また、自分の居る斜面の雪から上方の別の斜面で発生する雪崩を予測する ことはできない。いくら対策を講じても、雪崩に遭う確率はゼロには ならない。万一のことを考えればセルフレスキューも可能にしておく 必要がある。
北海道大学低温科学研究所 雪害科学部門 秋田谷英次教授ならびに 故福澤卓也助手には、遠征実施前の雪崩対策立案からザトルワラに おける雪崩の解析に至るまで、多大の御協力、御教示を頂きました。 感謝します。
1)日本雪氷学会編:雪氷辞典、古今書院.
2)HAJ北海道、札幌山岳連盟:海外登山研究会参考資料、1991.
3)北海道大学探検部ヒマラヤ遠征隊:ネパールヒマラヤ登山事故報告書、1987.
4)日本勤労者山岳連盟中央登山学校:
第7回「雪崩事故を防ぐための講習会」補助テキストpp33-47、1992.
5)Armstrong, B. R. and Williams, K.: The Avalanche Handbook.
Fulcrum Publishing (ISBN: 1-55591-119-6).