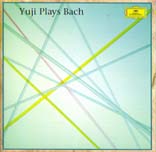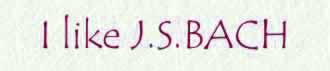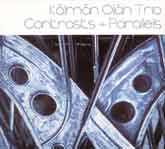無伴奏チェロ組曲 BWV1007〜1012
チェロ:マリオ・ブルネロ
これこそ無伴奏チェロ組曲のCDの決定版!といえる録音がリリースされました。
これほど味わい深く、一音一音耳を傾けながら、音楽に浸りたくなる演奏はめったにありません。
バッハの音楽を深く理解し、一度噛み砕いて消化してから、高いレベルでブルネロの奏でる音楽として
再構成されていると言っていいでしょう。
「決定版」といっておきながら、全くスタンダードではありません。
え?ここピチカートだっけ?とか、また流れるような旋律のようなものを期待してはいけません。
ブルネロの無伴奏を聴いたあとでは、以前のおすすめのモルクの無伴奏は非常に滑らかに感じます。
しかし、無人島に持っていくとしたら、今の私は躊躇することなくこのブルネロの無伴奏を選びます。
ここには素顔のブルネロの心があって、まるでブルネロと共に「バッハの無伴奏って良い曲だね」と
確認しあいながら聴いているかのような錯覚をもたらしてくれる演奏なのです。
音色・録音も深く沈みこむような豊かな広がりのある音で聴き惚れます。これはお薦めの演奏です。
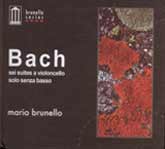
前奏曲とフーガ イ短調 BWV543 リスト編曲版
ピアノ : ヘレン・グリモー
アルバムの曲構成が、とても魅力的なCDです。(演奏の質も高いです)
平均律第1巻2・4番、協奏曲第1番、シャコンヌとオルガン用の前奏曲とフーガの編曲版。
バッハの作品のなかでも私の好きな曲が山盛りで、バッハをよく知りたい、という人に、
まずお勧めしたくなるCDです。
(バッハというとトッカータとフーガ ニ短調を紹介する入門CD等にはうんざりしています)
そして、どの曲も演奏の質が高いです。もちろん、大好きなバッハですから、それぞれに
「この曲は、あの演奏のほうが・・」と思う演奏もありますが、
(といいましても私の中でのベスト演奏との差は大きくはなく、実力伯仲のレベルです。)
次々に好きな曲が演奏される構成でもあり、「CDを入れ替えずに、このまま聴こう」と、
結局、プレーヤーの中にはいつもこのCDが入っていることの多いこの頃です。
演奏内容も、対位法の構成の魅力と、旋律の歌わせ方のバランスがよく、
曲がよく消化された(それぞれの曲のツボをしっかりおさえた)、魅力的なものです。
堅苦しくならず奇異にも走らない、いうなればキレと歌のあるオーソドックス・スタイルでしょうか。
素晴らしい。
このリスト編曲版は初めて聴きました。改めてオリジナルのオルガン版をヴァルヒャの演奏で聴いて
みましたが、私はオリジナルよりこちらの演奏の方が気に入りました。
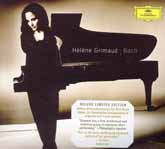
ゴルトベルグ変奏曲 BWV988
ピアノ : KALMAN OLAH . コントラバス : MINI SCHULZ
Stutgart Chamber Orchestra
これは、ひとえにKALMAN OLAHさんのピアノ即興演奏が魅力のアルバムですね。
弦楽四重奏版のゴルトベルグ変奏曲と、ジャズ版のゴルトベルグ変奏曲が交互に
演奏されるのですが、あまり好きじゃなかったこの曲が、とても魅力的に感じられます。
私はぎりぎりまで崩しきったモダン・ジャズにはついてゆけませんし、
さりとて硬すぎるクラッシックは煮ても焼いても食えん、と感じつつある近頃の私にとって
彼のピアノは、ちょうど匙加減のよい、バッハージャズ即興の味付けだったのかもしれません。
久しぶりに、買ってきたその日に何べんも繰り返し聴いています。お薦め!(左)
|
|
追記
KALMAN OLAHさんのピアノが気にいった私は、もう一枚ジャズ寄りのアルバムをj購入しました。(右)
Contrasts+Parallels
KALMAN OLAH TRIO
ゴルトベルグの3年後にレコーディングされたこのアルバムも、
前半は同様のゴルトベルグ変奏曲の即興を、トリオで演奏した発展形ともいえる演奏です。
ピアノの即興もよりひねってありますし、特に私はパーカッションの入り方を興味深く聴いています。
ときにジャズ的、ときにクラッシック的、ときに民族音楽的と、ボーダーレスの柔らかく上質な音楽が
素晴らしいです。ますますKALMAN OLAHさんの音楽世界のファンになりました。
ヨハネ受難曲 BWV245
指揮者 : 鈴木雅明 バッハ・コレギウム・ジャパン
美大浪人中、クラッシックへの嗜好が強くなり、またその頃、タルコフスキーの映画に
バッハのマタイ受難曲が使われていたのをきっかけに、マタイ受難曲のいくつかの演奏を
聴きはじめました。しかし当時、3枚組のCDを次々買うお金などなく、その意味でも
受難曲はハードルが高かったのですが、芸大に入学すると、膨大な量の音楽ソースの視聴室があり、
入学してからしばらくは視聴室に通い続けました。ヨハネ受難曲を初めて聴いたのもここでした。
迫りくる序曲を聴いたときには「こんなタイプの音楽は聴いたことない!」と嬉しい驚きがありました。
ただ、その後の長い受難の物語の進行には、正直うんざりし、飛ばし飛ばしアリアだけを聴きました。
それ以来「ヨハネは序曲と数曲のアリアだけ」と思い込んでしまい、ハイライト版とか買っていました。
しかし、(前置き長すぎですね・・・)このBCJのヨハネを聞いてビックリ。
美しい音色の響きと、キビキビとした緩急の流れによって、全曲をひとつにまとめ上げて聴かせて
くれます。歌詞と音符の両方を楽譜から読み切って、豊かな表現に置き換えないとできない演奏だと
感じます。 あっぱれ、バッハ・コレギウム・ジャパン。
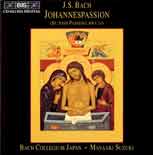
シャコンヌ ニ短調 BWV1004
ギター : 福田進一
これで1000円は破格の値段です!とにかく音色が美しいです。
演奏は真面目すぎるといいますか、優等生的な退屈感は若干ありますが、
シャコンヌのような、フーガが徹底的に入り組んだ曲では、
高度な技術とともに、そのまじめさが生きて構築性を高めて魅力になっています。

パッサカリア BWV528 ・ フーガ(平均率第1巻4番) BWV849
弦楽六重奏:フレットワーク
どうにもJ・S・バッハとその周辺の曲(時代的、あるいは音楽的に)ばかりを愛聴するという、
(閉鎖的)傾向の強まる私は、好きな曲の演奏のバリエーションを探し求めることが多くなっています。
このCDは、鍵盤楽器のために作曲されたバッハの曲を弦楽六重奏にアレンジして演奏しています。
アレンジされた作品がオリジナルと同等以上の魅力を持つ曲・演奏に出会うのは稀ですが、
このパッサカリアと平均率第1巻第4フーガ(ナイス選曲!)の入ったCDでは、
原曲の魅力を損なわず、弦楽器の柔らかい音色による新たな魅力を生みだしています。
本来、一人で演奏する曲を6人で分担するので、テンポやアクセントにおいて無難で退屈な演奏に
なりがちなことも心配しましたが、まるで一人で弾いているように息の合った魅力的な演奏です。

無伴奏チェロ組曲 BWV1007〜1012
チェロ:トゥルルス・モルク
チェロの中低音の響きの味わい深い魅力的な演奏です。
私はバッハの音楽を、
基本的には(対位法における)線の要素の強い音楽だと思っているのですが、
この演奏では、音の余韻とそこに次々に重ねられる(面的な)音の響きの美しさが
際立って表現されています。
そのため、旋律の聴きどころ以外にも「この曲にこんなに美しいところがあったのか」という
新鮮な発見をいくつも感じることができました。
この組曲を滑らかで美しい音の響きで聴こうと思うなら、この録音をおすすめします。
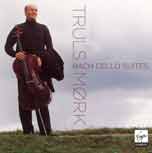
平均率クラヴィーア曲集第1巻 第4番 嬰ハ短調 BWV849 (特にフーガ)
ピアノ:スヴャトスラフ・リヒテル
流れるような左手の旋律がはじまってからの、
その中からきこえてくる3連符と主旋律のからみがなんともいえないです。
この左手の流れるような旋律と近いものが、
第二巻・第14番・嬰へ短調 BWV883のフーガにも登場します。
どちらの曲もすごく好きです。
平均率曲集は何人かのピアニストの録音を聴きましたが、私はこのリヒテル盤を
一番良く聴きます。たとえ叙情的過ぎると言われようとも・・・。
平均率クラヴィーア曲集第1巻 第24番 ロ短調 BWV869
ピアノ:フリードリヒ・グルダ
先の第4番と同じツボを押される名曲。
4番よりも良くも悪くも作り込まれているので、聞き応えがあります。
特に、フーガ・パートの壮大な展開が醸し出す曲の魅力は
バッハの真骨頂ここにあり!と叫んでもいいなぁと思います。
曲自体が壮大なので、リヒテルより少し軽快なグルダの演奏がいいですね。
パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830
ピアノ:グレン・グールド
この曲はひそかに私がグールドの演奏の中で一番気に入っているものです。
グールドというとゴルトベルク変奏曲を挙げる批評家が多いようですが、私はどうも
ゴルトベルク変奏曲があまり好きではないのです。
率直なところ、このパルティータ第6番とグールドの演奏の組み合わせが、最も私の好みなのです。
フランス風序曲 ロ短調 BWV831
ピアノ:グレン・グールド
壮大でドラマテックな序曲は、
叙情的な主題と舞曲らしいリズムで心地良く浸れます。
グールドの歯切れの良いテンポのおかげで、感傷的になりすぎずに
組曲全体の主題や展開の異なる趣向を爽快に味わえます。
シャコンヌ ニ短調 BWV1004
(無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ 第2番 第5楽章)
リュート:菊池 雅樹
ヴァイオリンの名曲であるこのシャコンヌは、多くのヴァイオリニストの名演がありますが、
偶然出会ったこの演奏の素朴な感情移入ぶりと、リュートの音色がツボにはまり、
スケッチなどの時にウォークマンなどでよく聞いています。
その後、CDショップなどで、この演奏の入ったアルバムを一度も見かけることがないので
売れずに第1版しか販売されてないのでは?(ジャケットのデザインが悪すぎた!)と思います。
フーガの技法 BWV1080
ピアノ:ゾルターン・コチシュ
バッハの対位法の集大成になるというこの曲の、作曲法的なことに関してはまったくわかりません。
管弦樂によるものやオルガンによるものなども聞きましたが、いまいち魅力を感じませんでした。
(フーガのように同一主題をストイックに展開していく曲の場合は、
音色をむやみに豊かにせず、むしろ単一音色で弾き通した方が、
曲展開の醍醐味を味わえる気がするのです。)
このコチシュのピアノ演奏では、フーガ展開の安定した構築感があり、
単一楽器で演奏しているためもあってか、和音として溶けこむところと
独立して離れて行くところの入り乱れる面白さが存分に感じられ、
難解に思われがちなこの曲を最後まで聞きたくなる魅力をもっています。
4台のチェンバロのための協奏曲 BWV1065
指揮・チェンバロ:トレバーピノック イングリッシュ・コンサート
この曲はヴィヴァルディの協奏曲「調和の幻想」第10番のバッハの編曲によるものです。
初めて聴いたのは、2003年のヴェルビエ音楽祭のDVDでした。
M・アルゲリッチやE・キーシン、J・レヴァイン、M・プレトニョフという
豪華で強い個性を持つメンバーが、抑制の効いたアプローチで一つの音楽を築き上げていく
姿が印象的でした。(弦楽器もG・クレーメル、M・マイスキーなど超豪華メンバーでした)
その後、CDでこの曲の良い演奏を探し、トレバーピノックの演奏を推薦する人がいたので
聴いてみたところ、細かいパッセージの豊かさと全体の端正な流れが美しく、
とても気に入りました。(この演奏と比較したのは、トン・コープマンの録音です。)
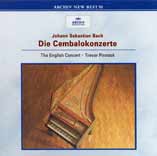
マタイ受難曲 BWV244
指揮者:カール・リヒター ミュンヘン・バッハ・オーケストラ
マタイ受難曲全体は3時間近い大曲なので、めったに通して聞くことはありませんが
この曲の序曲の”きたれわが娘たちよ”は、もう何度聞いたかわかりません。
聞く人をこの音楽のもつイメージの世界へ一気に引き込んでしまう凄さは
いつ聞いても舌をまいてしまいます。
コンサートに行くとボーイ・ソプラノの子供達が登場して、澄んだ歌声を聞かせてくれます。
演奏の好みは、、リヒターのような重みと思い入れのあるほうが
悲劇の世界へ引きずりこまれるには良いです。
(リヒターは「マタイ受難曲」を二度レコーディングしていますが、
もっぱら最初の1959年盤が評判がいいようです。
両方聞き比べてみると確かに59年盤のほうがメリハリがあってドラマティックです。
80年盤はもう少し瞑想するような深みを求めているような気がします。)
カンタータ 第150番 BWV150
指揮者:鈴木雅明 バッハ・コレギウム・ジャパン
とても繊細で美しい展開のカンタータ。
振幅の幅を限定しつつ大胆で細やかな展開を披露しているような魅力を感じます。
一番の聞きどころは、終曲の声楽とヴァイオリンの絡むシャコンヌのところです。
ドラマチックな、しかし不思議に静かな盛り上がりには
いまでも背筋がゾクゾクします。
初めて聞いたのは、NHK−FMの朝のバロックという番組でした。そのとき
「バッハの作品か疑う向きもある」と解説されたのが今でも気がかりです。
前奏曲とフーガ 変ホ長調 「聖アン」 BWV552 シェーンベルク編曲版
指揮者:エサ=ぺッカ・サロネン ロサンゼルス・フィルハーモニック
バッハの音楽の特徴は、”対位法の展開構造によるイメージ構築”
とでも言うべきところにある、と思っているのですが
それゆえに、楽器の音色にはあまり左右されないため、
後世の作曲者や演奏家による編曲版が多数存在しています。
この曲はオルガンの為に作曲されたものですが、
前奏曲のほうの演奏を聞くとシェーンベルクの管弦楽編曲版のほうが曲の構成の面白さや
音色の広がりが感じられるので、一聴の価値があると思います。
ただ、フーガの部分は「フーガの技法」と同じ理由で、単一楽器(オルガン)のほうが好きですね。
主よ、あわれみ給え BWV244 高橋悠治 編
ピアノ:高橋 悠治
マタイ受難曲第二部にあるこの名曲は、A,タルコフスキー監督の「サクリファイス」という映画で
印象的に使われていました。
原曲がアルトとヴァイオリンソロという音色の絡みの美しさの魅力が抜群な曲のため、
ピアノ版への編曲は困難であったようで、この演奏を聴くかぎり原曲を超えていないと思います。
そうでありながら、この“お気に入り”へ加えようと思ったのは、このアルバム全体の完成度ゆえです。
この曲の後には、先に紹介したヴァイオリンの名曲“シャコンヌ”
・オルガンの名曲トッカータとフーガニ短調のプゾーニ編曲版が続きます。
この3曲を通しで聴くと、高橋悠治の過飾のない、かつバッハの音楽構築に対する敬意と
積極的な賛同が感じられ、心地よく聞きとおす魅力にあふれています。