
その館は、錆びた青銅の門に続く深い森の中にあった。
「…何処まで行く気なんだ?」
砂利道のせいで、普段、乗り心地のよい筈の馬車も酷く揺れる。
小さくはない振動の中、クッションに背中を預けていた青年は不機嫌そうに言った。
「もうすぐ着くさ」
「…その言葉を何度聞いたか分からない」
ぷい、と顔を背けるが、生憎、馬車の窓には分厚いカーテンが下りていて外の景色はまったく見えない。しかも、何処へ行くのかという問いに対して、オレンジ色の髪の親友は『まあ、いいいじゃないか』の一点張りなのだ。
馬車に同乗しているのがラスティでなかったら、こんな誘拐同然のやり方、とっくの昔に飛び降りていることだろう。
「……」
向かいの座席に座っている親友は、さきほどからあまり言葉を発さない。おしゃべりな彼にしては珍しいことだ。しかし、外も見えず、会話も続かないとあっては、沈黙はただ重いだけだった。
幾度目かの溜息をついたところで、馬車が静かに止まった。
「…着いたかな?」
ほどなく、馬車の窓をノックする音。
ラスティは深緑色の天鵞絨のカーテンを開ける。
「…『鍵』をお持ちでいらっしゃいますか?」
黒いフードを被った男が馬車の外から問う。
「ああ。これだろう?」
彼は、ツィードのジャケットのポケットから何かを取り出し、男の白い手袋の上に乗せる。
それを、男はじっと見ていたが、それをラスティへと返した。
「…ようこそ。いらっしゃいませ」
口端に漸く笑みを浮かべ、男は恭しく頭を垂れると、馬車の扉を開けた。
「どうも」
ラスティは、ひょい、と馬車から飛び降りる。
革靴が踏んだのは、砂利などではなく御影石のアプローチだった。
いつの間にか、馬車は豪奢な屋敷の玄関へとつけられていたのだ。
「アスラン!早く来いよ」
さっさと馬車を飛び降りたラスティは、まだ、背もたれに背中を預けたままの親友を呼ぶ。
「…やれやれ」
完全に相手のペースに乗せられている。だが、此処まで来てしまったら、毒を喰らわば皿まで。そんな心境で、アスランは馬車を降りた。
「…何なんだ。此処は」
アスランは、翡翠の瞳を見開く。
重厚な石づくりの洋館。樫の木の扉が両側に開かれている。その奥は、玄関ホールだ。正面には、漆で黒く塗られたモダンな階段。床には緋色の絨毯が敷き詰められ、階段の両側には大きな壷が置かれ、椿や雪柳…季節の花が豪奢に活けられていた。
「いらっしゃいませ。黒鹿鳴館へ」
その声に、アスランは振り返る。そこには、さきほどのフードの男が立っていた。
下手のよい、漆黒のスワロウ・テイルの上にマントを羽織った男は、黒い仮面で顔を隠していた。
「…で。何なんだ?一体、此処は」
通されたのは、モダンな玄関ホールを裏切るような、和室の広間だった。
まるっきり洋風の廊下からひとつ扉を隔てると、まるで内玄関のような絨毯敷きのたたきがあった。そこから一段高くなった檜の廊下には障子。女中が其処を開け放つと、中には純和風の広い座敷があったのだ。
畳の上に置かれた分厚い座布団。そこに胡坐をかいているふたりの前には漆塗りのお膳がおいてある。その上には、軽い料理と葡萄酒の入った硝子の洋杯が並べられていた。
「ん?もうじき分かるさ」
やはり、アスランの問いには答えず、ラスティはさっさと洋杯に口をつける。
まるで、方向を見失わせるかのごとく、街中をぐるぐると馬車で走らされたことといい、カーテンを閉められていたことといい、この館の瞬らしいさきほどの仮面の男といい…かなり胡散臭いことこの上ない。
元より、物事を白黒させないと気がすまない性格だ。苛々がピークとなったアスランの耳に、まだ少し高い子供の声が響く。
「…お待たせいたしました」
すうっと、再び障子が両側に開かれる。
そこにはひとりの女が三つ指をついて頭を垂れていた。
その身に纏っているのは、黒地に鮮やかな色で牡丹や菖蒲、菊など、四季の花々を艶やかに彩った豪奢な打ち掛けだ。
大きく抜かれた襟からみえる肌は透けるように白く、とても艶かしい。
「……」
突然現れた実物大の日本人形。アスランは唖然とする。
「ああ、花紫、よく来てくれた。こっちに!」
ラスティの言葉に、彼女はゆっくりと顔を上げる。
その仕草で、重いくらいにつけられた鼈甲のかんざしがしゃらりと音を立てる。
鳶色の髪は優美に結い上げられ、たくさんのかんざしで飾られている。
伏眼がちな目元は、ぽってりとした唇と共に紅に彩られていた。ゆっくりとした動作で彼女は立ち上がる。
衣装が重いのだろう。両側から小間使いの少年が彼女の手を取って支える。
その刹那、ちらりと少女はアスランの方へと視線を走らせる。
「…!…」
吸い込まれるかとおもった。
その深い、夕暮れの色をした紫水晶に。
「花紫、おまえもこちらへ来ないか?」
葡萄酒にほろ酔い気分のラスティが声をかける。
「…いえ、わたくしは」
しかし、彼女はゆっくりと首を横に振る。そのはずみに、またかんざしが軽やかな音を立てた。
それは、等身大の美しいお人形だった。
彼女が宴席の相手をしてくれるのかと思いきや、彼女の後から歳の若い芸妓たちが室内へ入ってきて、歌や舞を披露し始めたのだ。
次々と運ばれる懐石の運び出しや、酒を注ぐのも他の女たちの仕事。
美しく着飾った彼女は、と言えば、まるで置きもののように座り、ただ其処に居るだけだった。
ここまで来て、アスランにもようやく此処がどういう場所かがはっきりと分かった。おそらく、話にしか聞いたことのない『遊郭』と呼ばれる場所なのだろう。
次々と、繰り広げられる三味線や太鼓のお囃子や唄は、アスランにとっては煩いだけだった。
しつこく酒をすすめてくる芸妓の誘いを適当に受け流しながら、ちらりとアスランは違う方角へと視線を走らせる。
宴席が和やかになるにつれ、他の芸妓たちが距離を詰めてくるのに対し、彼女は最初の凛とした雰囲気をまとったまま、お人形のようにただ座っていた。
何度かラスティが話しかけていたが、彼女は、淡い笑みを浮かべ、一言、二言返すだけで、会話が続くことはなかった。
(気位が高いのかもしれないな)
美しい女は得てして矜持も高いものだ。彼女もその例に違わないのかもしれない。
そういえば、よくよく考えてみると、彼女が座っているのは部屋の上座だ。金を払う客を下座に座らせておいて、自分が主人面して上座に座っているだなんて、可愛い顔をしてなかなかにふてぶてしい。素直にいい感情を抱くことは出来なかった。
「お酒のおかわりをどうぞ」
「…ああ、ありがとう」
芸妓が黒塗りの銚子を勧める。
漆塗りに金蒔絵の杯でアスランはそれを受けた。
杯に口をつけていると…不意に視線を感じる。
顔をそちらに向けた刹那、少女と視線が交錯する。
「……」
行灯の仄かな光を受け、紫水晶の瞳が揺れる。
その、物言いた気な瞳に…この時から魅入られていたのかもしれない。
「…名前は?」
「え?」
その言葉に、彼女は小さな声を返した。
酒の勢いを借り、アスランはゆらりと立ち上がると、彼女へと近づく。
「ちょ…アスラン!」
慌ててラスティが制止するが、アスランは意に介さず彼女の前へ膝をつく。
「……」
驚いたように、紫の瞳が見開かれている。それは、春に咲く小さな菫の花の色にも似ていた。
「名前を…教えてくれないか?」
あまりに熱っぽい視線に、彼女はすっと瞳を伏せ、小さな声で言った。
「…花紫と申します」
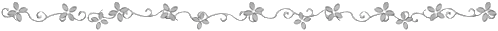
「姐さん、もうすぐお客様がお見えらしいぜ。支度はもう出来たのか?」
「…はぁい」
自分の部屋でカウチにごろりと横になっていた鳶色の髪の少女は、お返事だけでまだ読んでいる本から視線を外そうとしない。
そんな様子に、カウチの下で寝そべっている少年が彼の名を呼。
「…ヒビキ。さっき、スティングが言ったこと、聞こえなかったのか?」
スティングというのは、さきほど部屋の外から声をかけた少年の名前だ。
「ん?あとちょっとは大丈夫だよ」
さらりとそう言って、彼女は再び読書に没頭してしまう。
傍らでお菓子をかじっていた水色の髪の少年は、はあ、と溜息をついた。
「まったく、ヒビキは呑気なんだから」
「慌てたっていいことなんて何もないでしょ?いいの、いいの。客は待たせておいたら。それよりアウル、此処では僕のこと『ヒビキ』って呼んでもいいけど…」
「宴席では『花紫』か『姐さん』だろう?分かってるよ」
もう何度も同じことを言われている。うんざりとしたようにアウルは繰り返した。
「うん。僕は別に気にしないんだけど、花魁を源氏名で呼ぶのは館のしきたりだから。ごめんね」
そう言って、当代一の花魁である花紫――ヒビキは苦笑した。
『太夫』クラスの花魁ともなれば、毎晩のように通う上客以外であれば客の方が立場は下だ。ヒビキは自分の価値を正しく理解していた。
のんびりと、読書を楽しめる時間なんて、仕事がはじまる前のこの時間しかないのだ。
今だけは、ヒビキに花魁の片鱗もない。歳相応の子供のような好奇心旺盛な瞳をしていた。
「でも、確か、今日の客は、なんとか男爵だったぜ?」
「…へえ?誰だろう」
ヒビキは、自分の上客の中から爵位を持つ人物を思い起こす。
長い間、日本を支配した江戸幕府が倒され、明治という新しい時代が生まれた。それと共に、これまでの身分制度は一転した。
士農工商というように、武士を頂点とした序列から、天皇を頂点とし、すべての民は平等であるという四民平等に変わったのだ。
しかし、実際のところ、すべての人々に対して平等な世の中ではない。
公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵と呼ばれる天皇家を支える貴族たち。そして倒幕に力を貸した薩摩、長州、土佐出身の武士、華族。
彼らと一般市民との間には、大きな隔たりがあった。
そして…時代が変わっても、ヒビキのように身寄りがなく、気付けば遊郭に売られていたような子供にとって、いくら政府の掲げるお題目が変わったところで毎日の生活に何の変化がある訳でもなかった。
「…あれ、花紫。まだこんな処に居たのか?」
その時、扉の向こうから剣呑な男の声が聞こえる。
漆黒の礼服を纏い、黒い仮面で顔の半分を被った金髪の男だ。
「ああ…ネオさん」
「ネオさん、じゃないだろう。もうすぐお客様がいらっしゃるぞ。ちゃんと支度をして出迎えろ」
カウチに寝転ぶヒビキは、紅い襦袢一枚のあられもない格好だ。
男はのんびりとくつろいだ様子に呆れたようだった。
彼はネオ・ロアノーク。この『黒鹿鳴館』の館主だった。
客が来れば、玄関で馬車の扉を開けて出迎え、帰る際には最後までお見送りをして『またのお越しをお待ちしております』と言うのが彼の仕事だった。
「…はぁい」
煩いの、と小さく呟きながらヒビキは読みかけの本に栞を挟んだ。
「…アウル。おまえ、ちゃんと花紫の面倒見ろよ?」
「うるせーな。分かってるよ!」
水色の髪の少年が元気よく返事をする。アウルは吉原風に言うならば、花紫太夫付きの『振袖新造』といわれる妹分のような存在だった。さきほど、声をかけたスティングも同様だ。
このほかに、吉原ならば花魁には『禿』と呼ばれる身の回りの世話をする子供もついているのだが、此処では振袖新造であるふたりがその役目を果たしていた。
カウチから起き上がったヒビキは鏡の前に座ると、ほつれている遅れ毛をなでつける。大きく背中が見えそうなほどに抜かれた襟元や、着物の袖から白い肌がちらりと見えた。それは、彼を『商品』としてしか見ることのないネオにとっても酷く扇情的だった。
「ネオさん、今日のお客様ってどなた?」
「ザラ男爵だ」
壁にもたれたまま、ネオはヒビキが支度する様子を見ている。
「…ザラ男爵…?あぁ…」
確か、先日、外国人の男たちと共に宴席を設けた人物だ。まるで鷹の瞳のように鋭い眼光をもっていた。時折、ここで宴席を設ける貴族のひとりだった。
アウルが差し出した鼈甲の簪を、ヒビキは器用に自分で鳶色の髪へと挿してゆく。
「…ってことは、今日も宴会?ネオさん、その人、きっといいお客様になるね」
そう言いながら、ヒビキは紅を小指の先に取る。
うっすらと開かれた唇。細い指が、すうっと唇をなぞってゆく。
その動きにともないヒビキの唇は鮮やかな紅色に染められる。
化粧直しが終わると、ヒビキはすっと立ち上がる。その背中に、アウルが背伸びをしながら重いうちかけを着せ掛ける。
黒地に、今が盛りの赤と白の椿を染め抜いたその着物は最高級の京友禅だった。
ぴしりと襟をひっぱり、金糸や銀糸を織り込んだ西陣の帯を結ぶ。
吉原風に、後ろで結わずに前で軽く結んで長く垂らした、だらり帯だった。
もう、さきほどまでの寛いだ空気はどこにもない。
そこには、『黒鹿鳴館』一番の花魁、一晩で男を虜にするという花紫太夫の姿があるだけだった。
*Comment*
年末だったか、年始だったかに、三島由紀夫の『鹿鳴館』のドラマをちらっと見て…明治いいかも!とちょっと盛り上がったわたくしとあじさん。
そういうわけで、鹿鳴館時代を書いてみました。ちなみに、こちらのイラストは本の裏表紙になっているのですが・・・クレジット入れるの忘れていたことを入稿してから思い出したよ・・・。
Azureさま。本当にすみません。いつもありがとうございます。
ちょっと、今回はいろいろとアクシデントがあったのですが、頼んでいた資料が原稿を書くまでに手元に届かなかったというのが最大の敗因・・・。ちょっと時代考証が甘い感じもしますが、お許しください。
この前編にあたるエピソードではキラの名前は『ヒビキ』になっています。
そのため、最初は違和感があるかもしれませんが、ご容赦を。(あたしも途中、何度もタイプミスしてました・・・)
後編は、10月くらいにお届けできたらいいなぁと思っています。
もし、気にいってくだされば、少し間があきますが待っていていただけると嬉しいです。
2008.Mar
綺阿。
Thank You For Illustation Azure**SAMAv
©Kia - Gravity Free - 2008
