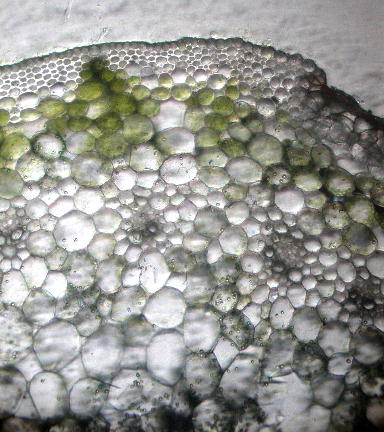
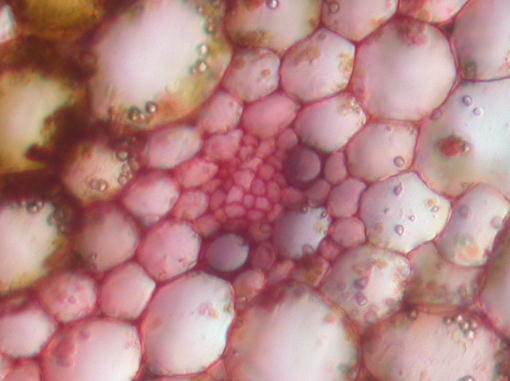
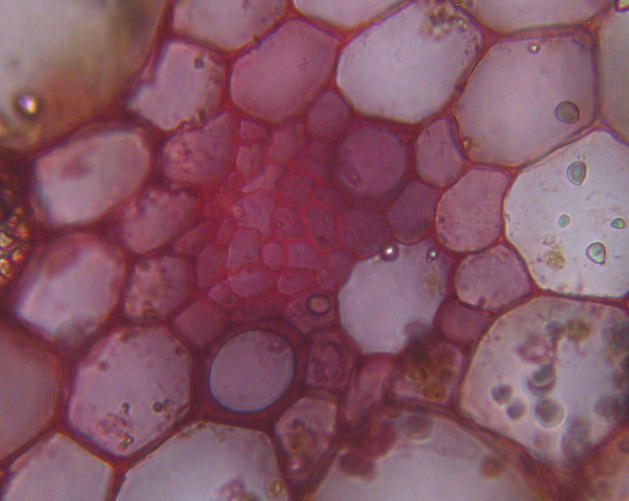

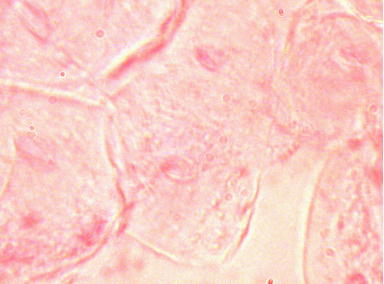
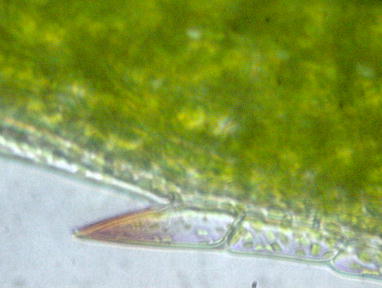
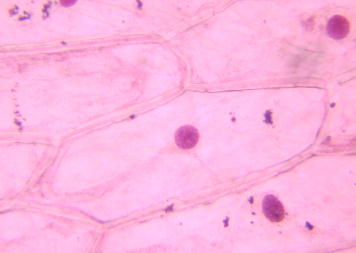
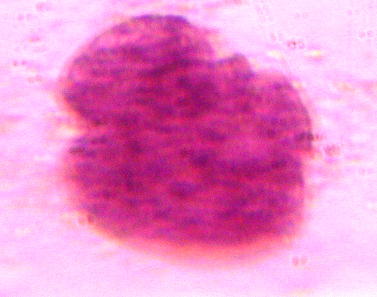
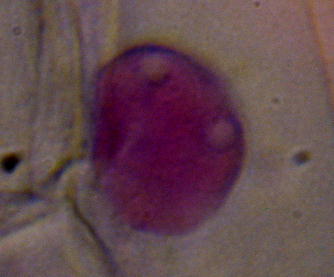
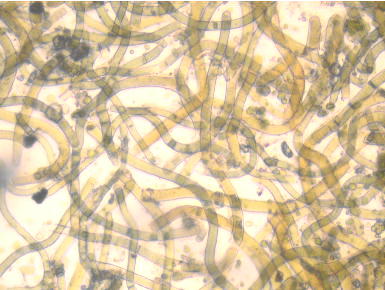


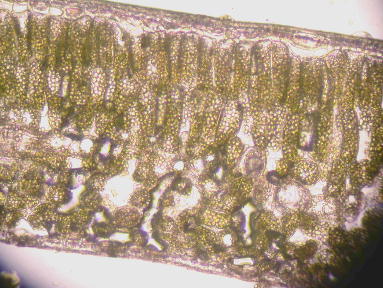
 孔辺細胞には他の表皮細胞とは異なり、葉緑体がある。
孔辺細胞には他の表皮細胞とは異なり、葉緑体がある。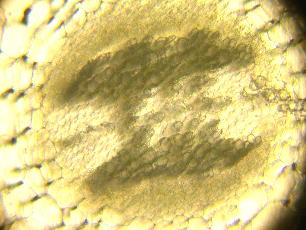
 実習助手のSさんに簡易ミクロトームを
実習助手のSさんに簡易ミクロトームを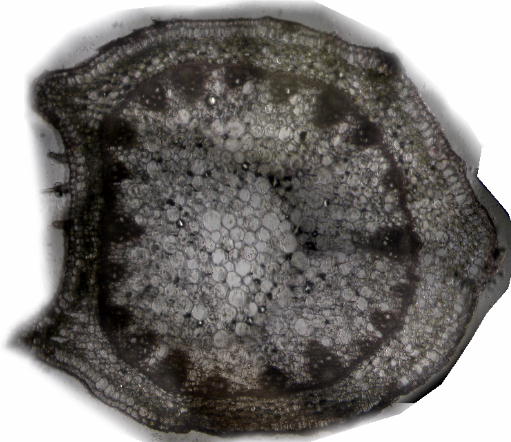 数枚の写真を貼り合わせた合成写真です。
数枚の写真を貼り合わせた合成写真です。
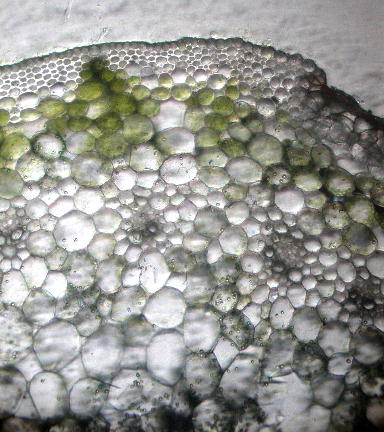 |
茎断面(一部)。染色していないので、維管束の位置がはっきりせず、また、 より茎の中心部の部分が写されていないので、写真ではわからないが、 維管束は散在している(単子葉植物の茎の特徴)。 |
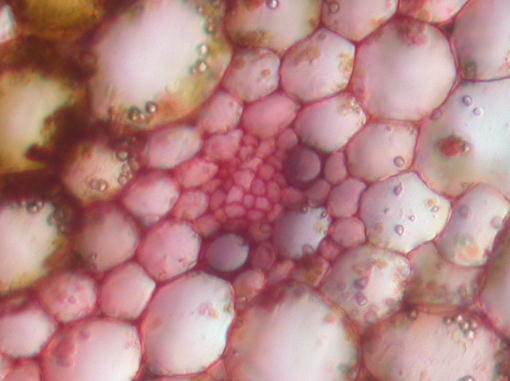
| 維管束断面の拡大。細胞壁が厚く、目のように見える2つの導管と口のように見える破生間隙が わかる。単子葉植物なので形成層は見られない。(サフラニン染色) |
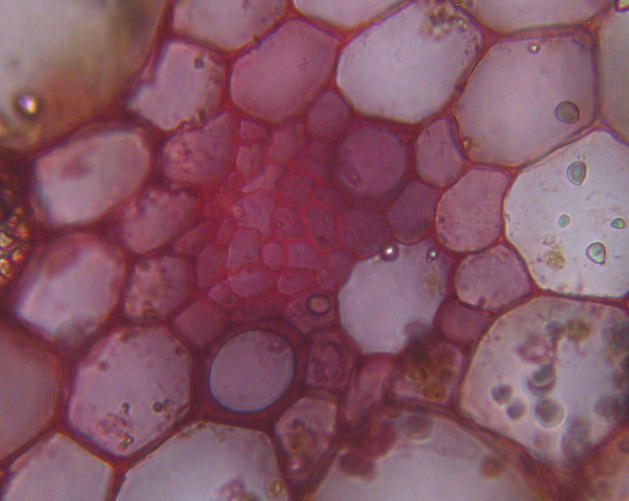
|
さらに拡大すると、導管の間から外方向(画面左上)の師部の様子がよく分かる。(サフラニン染色) |
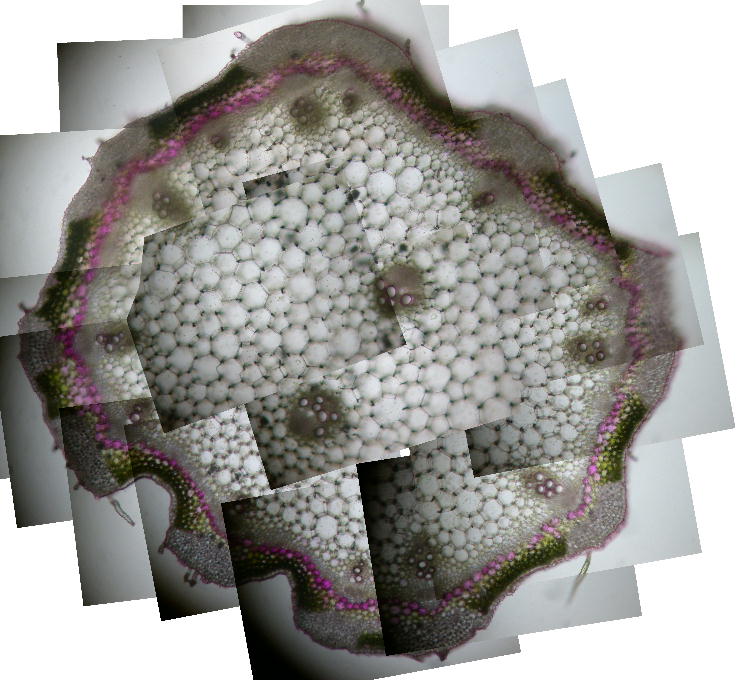 中央の2つの維管束の意味するところは?
中央の2つの維管束の意味するところは?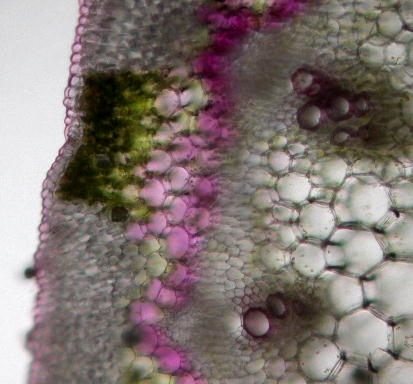 一部分の拡大
一部分の拡大 維管束の拡大
維管束の拡大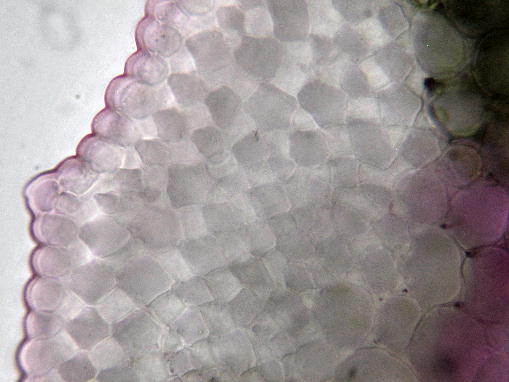 厚角組織
厚角組織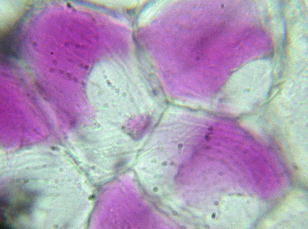 ショ糖高張液中
ショ糖高張液中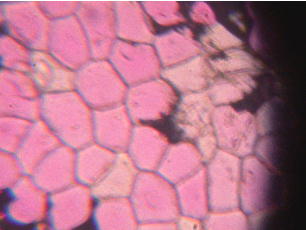 水道水中
水道水中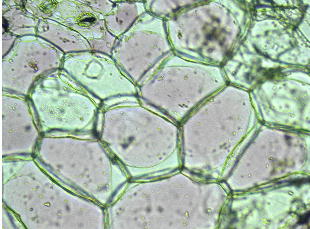 ショ糖高張液中
ショ糖高張液中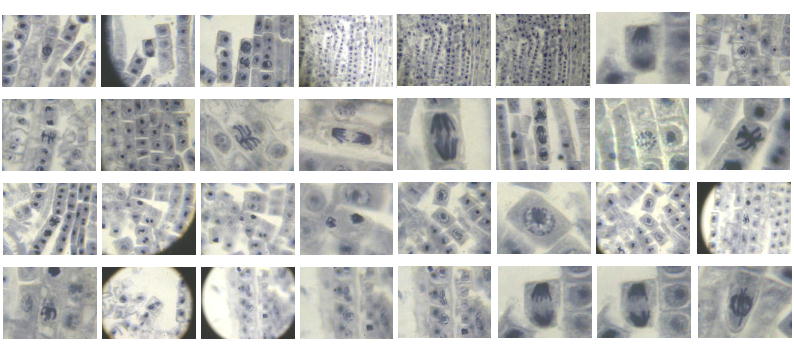 永久プレパラート使用
永久プレパラート使用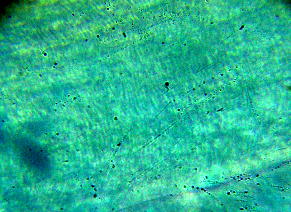 筋細胞の横紋
筋細胞の横紋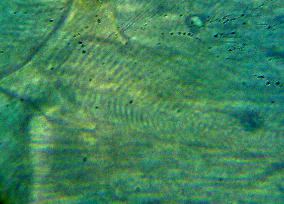

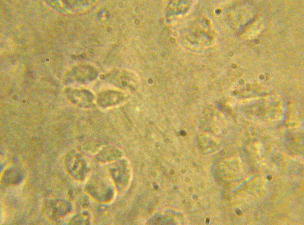 軟骨組織
軟骨組織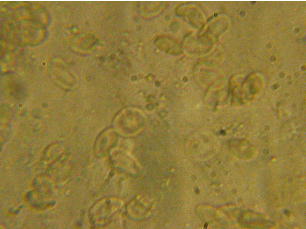 骨髄からの細胞
骨髄からの細胞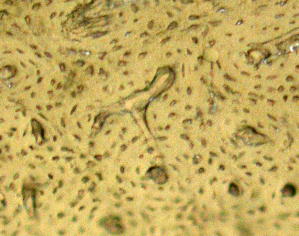 骨組織
骨組織
乳酸菌 サーモフィルス菌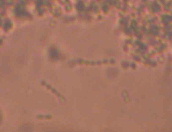
|
市販のヨーグルトのうちM社のも
のにはサーモフィルス菌という乳
酸菌が入っている。これは連鎖球
菌なので、見つけやすい。(写真左) 「乳酸菌」は乳酸発酵する細菌の 総称。 ヨーグルトメーカーに牛乳と市販 のヨーグルトを入れて、ヨーグル トを増やす。(写真右) |

|
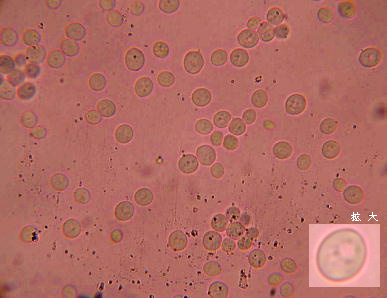 酵母菌
酵母菌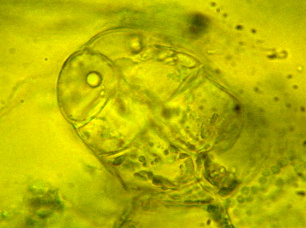 前葉体を顕微鏡下で観察すると、造卵器の上部が突き出ているのが見える。造精器らしいものもみえるが、それとはっきり確認できないので、写真は掲載しない。
前葉体を顕微鏡下で観察すると、造卵器の上部が突き出ているのが見える。造精器らしいものもみえるが、それとはっきり確認できないので、写真は掲載しない。
 アカムシ(ユスリカの幼虫)の頭部を柄付き針で押さえて、胴をピンセットで引っ張ると、頭に続いて消化管とともに唾液腺が一対出てくる。他の臓器と紛らわしいので、生徒には予めビデオや写真で例を示しておくとよい。左下写真のような形の透明な臓器である。 アカムシ(ユスリカの幼虫)の頭部を柄付き針で押さえて、胴をピンセットで引っ張ると、頭に続いて消化管とともに唾液腺が一対出てくる。他の臓器と紛らわしいので、生徒には予めビデオや写真で例を示しておくとよい。左下写真のような形の透明な臓器である。←アカムシ(ユスリカの幼虫) 黒い方が頭 |
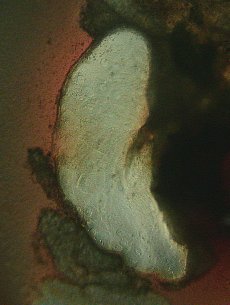 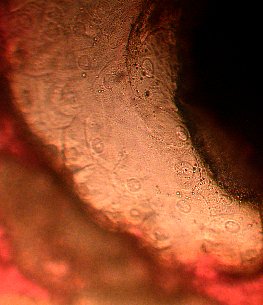 左 唾液腺の形 /右 唾液腺の細胞 酢酸オルセインで染める前に、カバーガラスをかけず、低倍率(×150)で検鏡すると、唾液腺の細胞がわかる。これを確認してから、染色し、カバーガラスの上から軽く押して、高倍率(×600)で検鏡する。 |

 生徒の見つけた唾液腺染色体 |
