|
飯草(4)栗木に在住しているが、昔は柿生中学一校しかなかった。(現在は、昔の学区に五校の中学があります。)
小松(17)今回を機会に同窓会活動に微力ながら頑張っていきたい。昔の関係は非常に大事である。
堀田(45)現在川崎市の公立中学校の教員をやっているが、新しい仲間を増やしていきたいと考えています。
山田秀樹(20)現在の同窓会についてはほとんど知らなかった。活発にしていくためにはどうしたら良いか考える必要がある。自分たちの同期会は六月に行い、一六二人中九〇名弱、先生方三名に来て頂いた。今後の活動は、各期の理事を中心にクラス会を起こすなどスタートしていくべきである。
山田譲(20)三〇周年の時に役員をやった経験がある。今年同期会をやったので、これを契機に始めていきたい。
校長 私は富山県出身で35年に中学を卒業しました。母校の同期生に三人の永久幹事がいてクラス会など面倒を見ています。ボランティア精神がなければ、こういったことは続かないと思います。柿生中学の卒業生では森谷さんと古くからの知り合いです。
尾作(24)平成十一年(九十名)と平成十三年(四十名)に同期会を行った。まだ地域にいる同期生も多く連携を深めていきたい。
高津原(29)元東柿生小学校の教員で、本日参加の堀田さんは教え子です。二十九期は同期会をまだ開いていない現状です。子供が中学に入る年代になってきたので、コミニュケーションを深めていきたい。学校行事にも顔を出していきたい。
梶(23)同窓会活動が充実してきたところだと思います。各期の理事については、本人もわかっていない現状があると思います。同期会を行うことが大事だと思います。レクリエーション活動などを期を越えて実施していくことも検討していきたいと思います。
鈴木(15)三年前に五回目の同期会を行い、その時の様子を同窓会報第二号に掲載した。アンケートの結果五年おきに同期会を実施することになっている。七人の同期生が亡くなっているが、歳をとったら毎年やっていきたい。 
|
渡辺(12)同窓会活動の活性化を図る妙案はなかなかないと思うので、現在の行事(同窓会報と入会式)をきちんと実施していくことが重要である。
河上(23)二十三期は三年前に二十八年ぶりに同期会を新百合ヶ丘ホテル「モリノ」で行い、その後毎年地元の人たちを中心に集まれる人で小規模に実施している。剣道部に所属していたが、学年を越えた縦のつながりも重要だと思う。クラブ関係の連絡はとることができない。
教頭 教員が連絡を取っている例はある。
校長 高校は顧問とのつながりが強く中学は少し弱いのが一般的のようだ。
鈴木(15)同窓会活動の広報をPTA会報に載せてもらうことも考えてみてはどうか。
校長 学校で行う活動は管理者として説明責任がある。同窓会活動については告知が必要だと考える。
渡辺(12)「うれ柿」等の例があるが、同窓会についても名前がないのでそろそろ考える時期である。
鈴木(15)この一年の課題としてはどうだろうか。
本多(23)会報に名前がつけばインパクトがある。同窓会報の持つ意義は非常に大きいと思う。
渡辺(12)インターネット上にもHPを持っているわけだが、会報の発行とともに毎年の更新が必要であると思う。毎年の会報作成をしないと役員としても集まれない。
校長 もう一つの大きな活動である入会式だが、今年の様子を見て大変すばらしかったと思います。同窓生の方ができるのはスゴイことだと思います。歴史のある学校だからできるのでしょう。普通の学校ではなかなかできません。
教頭 昨年度の佐藤さん(二十三期)の演奏には大変関心している。
個人的には、佐藤さんの中学時代の理科の研究(くもの研究)を通じて知っていた。次は保護者にも案内を出していきたい。
鈴木(15)演奏はすばらしかったので、入会式以外にも是非地域の人たちに聞いていただく機会を設けてみてはどうか。
校長 入会式にだけの演奏ではもったいない。 来年は、保護者にも声を掛けていきたい。 
|
間中(22)二十期に兄がいた。現在三年の学年主任なので本年度の入会式は盛り上げていきたい。
今の柿中の子供たちは素直な子供が多い。同期会の連絡は数回あり、理事以外人たちの声かけで集まった。みんな会いたいといっているようだ。
河上(23)理事や常任理事などの役員の決め方(かわり方)がわからない。
渡辺(12)理事の交代は各期でOKである。各期の役員や消息については現在では入会式時に「移動連絡ハガキ」を渡している。役員はボランティア精神がないとできない。
本多(23)ボランティア精神があっても、数人の組織で動いていなければ存続は難しいと思う。役員交代のシステムができなければいけない。同窓会再編の立ち上げ時からかかわっているが、私もいつまでできるかわからないので、特に地元(今の柿中の学区は上麻生と下麻生と岡上と王禅寺)で若い人たちがスタッフにどんどん加わって欲しい。せっかくここまでつないできたので、人がかわってまた休眠状態になってしまうことだけは避けたい。
河上(23)事務局でうまく対応していくことが大事だろう。
山田(20)規約上、理事の数を一〜四名に変えてもいいのではないだろうか。特に九州の人など理事としての活動は不可能だと思う。また、会報の同窓会レターに載せた期の人たちには全員配布してはどうだろうか。
本多(23)理事名簿については、三十周年の時からのものを継続させている。同窓会報はその理事の方々に毎回送付しているが届かない期もでてきているのが現状だ。
会報は毎回2000部作っているのでどんどん活用して欲しい。
理事については規約上、特に決まりはないので再構築する時期だと思う。また将来的には同窓会室がどこかに欲しいところだ。
渡辺(23)会報の配布については会員個々に送付は不可能なので、理事を活用していくしかないのが現状だ。
鈴木(15)十五期は会報第二号に同期会報告をし、人数分をいただき全員に配布した。また、些少だが寄付を募ることができた。
ということで、まだまだ時間も尽きないところですが、皆さんのご意見を反映させ益々同窓会が発展していくことを願って座談会を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。
|


 同窓生入会式報
同窓生入会式報![]()
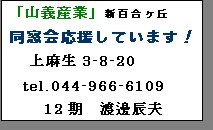
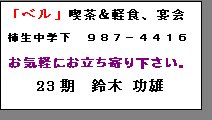
![]()