| 2000/9/15
第3号 戻る |
||
 |
柿 生 中 学 校 同 窓 会 報 |
|
| 2000/9/15
第3号 戻る |
||
 |
柿 生 中 学 校 同 窓 会 報 |
|
|
柿生中学今昔 |
 写真上 1966年(S41) 写真右 1984年(S59) |
| 特集
「柿」 の由来 「柿生」と聞いて思い出す果物の柿は、同窓生の方のほとんどは「禅寺丸」をイメージするのではないでしょうか。改めて柿についての歴史・由来を探ってみたいと思います。 写真1は、王禅寺境内の石碑に刻まれた北原白秋の詩です。柿の色合いと秋の様子を詠んだ、季節感あふれる詩だと思います。おそらく白秋は視覚ばかりではなく、禅寺丸の味にも舌鼓を打ったに違いないことでしょう。 ところで、王禅寺は延喜十七年(九一七年)高野山の第三世無空によって創建されたといわれていますが、元弘三年(一三三三年)鎌倉攻めの新田義貞の軍勢により消失してしまい、その後、建徳元年(一三七〇年)朝廷が等海上人に再建を命じました。等海上人は立派なお寺を建てようと用材を求めて山中深く入りました。その折、秋の日差しを浴びて輝く柿の木を見つけ、その実があまりにもおいしいので、その枝を接ぎ木して村人たちに栽培を勧めました。これがこの柿のはじまりとされ |
|
| 禅寺丸は枝つきのまま売られる枝柿として広く知られていますが、交通機関の発達していない頃は、四つ手車に積んで丸一日かけて神田の問屋まで運んだ記録があります。弘法の松の坂、登戸の渡し、三軒茶屋、赤坂見附という道筋だったようです が、自動車で行くならともかく当時の人々の大変さがわかるような気がします。 禅寺丸が一般に評価を得た時代は、明治末期から大正時代だったようです。郡や県での農産物品評会で賞を得て大変評判になり、明治四二年には宮内庁へ禅寺丸献上というはこびとなり、名実ともに地域の特産物となりました。販路の拡大など夢も大きく広がり、大正一〇年頃にはピークを迎えましたが、その後、生産も減少してしまいました。昭和七年の柿生村、岡上村は郷土の特産品として、近くを通る人々に即売所で売るなどしている光景は見かけるものの、手間をかけて売る人も次第に少なくなってきているのが現状のようです。しかし、このような状況に憂いを感じる人々も多く、「禅寺丸保存会」が結成され、この地域の特産物の復活に力を注いでいます。 |
私が柿生中学在学当時(昭和四〇年代中頃)と現在とでは、中学校周辺の景色も一変してしまいました。柿の木がたくさんあった場所も今では住宅地に様変わりし、野山で授業をさぼって柿をかじるなどといった、ほのぼのとした光景を見ることはまずないと思います。 |
| あれこれ十七年 旧職員(S30・1~S47・3在職) 森田 忠助 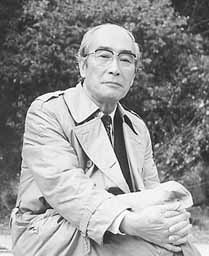 ・東京農大を出て教員の採用面接に学校へ行くと当時の学校長故磯岡寛にお会いした。「君は酒を好むか」との質問があり「私は梯子酒が大好きです」その一言で採用決定、面白い校長先生だった。 ・東京農大を出て教員の採用面接に学校へ行くと当時の学校長故磯岡寛にお会いした。「君は酒を好むか」との質問があり「私は梯子酒が大好きです」その一言で採用決定、面白い校長先生だった。・当時の学校の玄関は富士山側にあり、小学校とつづきで小学校長岡本先生の家が境界の処にあった。 ・柿生小学校が片平の田んぼの中に建つ計画が出来上がったので、その埋立て地の土を小学校から運んだ。今の体育館前の傾斜にその後が伺える。当時ブルトーザーが無いのでレールを引き手押しのトロッコで、ダンプを下の道に置いて商店街を通って運んだ。だから今の小学校のグランドには旧小学校の土地が入っている。 ・当時学校に上るには、削っただけのその坂道に杭を打ち階段が作ってあった。その道のそばに花桃の木を生徒と一緒に約百本植えた。春になるとすごく奇麗に咲き見事だった。 ・通勤には今の商店街を通ったが、雨が降ると大変。世田谷─町田線がまだ無かったので、車は全部商店街を通っていたので水たまりが出来て炭俵 |
や平木の板が置かれ、それをわたって通学をした。 ・学校下にトンネルがあった。くぐると左が山、右が谷でその谷間に女の人の死体が発見された事があった。(未だに未解決との話)・毎年お不動様のお祭りがあった。その日は先生も生徒も朝から落ち着かない。授業を半日にしてダルマさんを買って帰るのが楽しみだった。 ・秋の一月、全校のスケッチ大会が弘法松で行われた。学校裏よりトンネルの上を通って細い尾根を一列に並んで行った。一本の松の木は根本が焼け、一本の松の木が雄大な姿を見せてくれた。 ・まだ水道が無かった。山側に深く掘った井戸と家庭科教室の二カ所であった。朝早く用務員の中山さんがバケツで朝のうちに汲み上げそれを大きな釜に運びお昼のお茶に用意された。しかしその水も時々渇水になり困った。 ・校長室にクジラのヒゲがある。長さ五米位。これは私の友人が南太平洋で捕鯨禁止前にお土産に持ち帰ってもらったもの。あまり大きくて家に置く事が出来ないので学校へ持っていった。 ・次にトイレの話。きたない話だがドボンと落ちる形。困ったのはそれが一杯になったときの話。勿論汲取車は上まで上がって来れるはずはない。生徒と一緒に山側に大きい穴を掘ってそこにみんなと肥桶をかついで捨てた。それでも入らない時は、土手に流し近所の方々から注意をうけた。 ・困ったことが起きた。それは柿生地区に伝染病(赤痢)が大流行した時だった。保健所が来て、校舎内外の大消毒。そうして生徒の中にもかかったものもいたので、図書室の隅に衝立を立てて外から見えないようにして、一人一人ガラス棒をお尻に入れられて検便をうけた。・運動会が愉快だった。なにしろ運動場が狭いため走るのは円形のグラ |
| ンド。何度も廻って目が廻る。その中で生徒は一生懸命に走った。 ・嬉しかった事は女子テニスの顧問をしていた時。市内の三大大会を全部優勝で飾った事。当時はどことやっても強さ抜群。高校へ行っても勝っていた。そのカップを文化祭に披露した。・卒業式は勿論体育館が無いので、三教室をぶち抜いて校長先生の話と証書の授与式が行われた。細長い式場で、今考えるとよくしたものだなあと思う。 ・年一回の文化祭も盛大に行われた。生徒の皆さんをはじめご父兄の皆さんが来られ、お祭りさわぎ。クラス毎の劇が見ものだった。 ・次に台風の話。何年か忘れてしまったが、伊豆半島から柿生地区にかけて大台風が襲撃。それはそれは恐ろしかった。一夜明けてみると地区内のいたる所に、山くずれ、崖くずれがあって人家も押しつぶされていた。今ではその跡地に何事もなかったようにマンション、新築の家が多数建っているが、くずれやすい土地だけにこれからどうかなと心配している。 ・学校の坂道を上ったすぐ上の四階建ての校舎の下が晴天の日の朝、水でえぐりとられ足だけ残って土砂が下の道をふさいだ事もあった。原因は校舎の下に水道の水がたまって一度に吹き出したらしい。あと三十分おそかったら、登校中の生徒がまき込まれていた。でも人がくずれた土砂に入っているという話が出て、全校生徒の安否を学校から問い合わせたが、こんなになった事を初めて見たので驚いた。 ・一年一度の校内マラソン大会が柿生小前より黒川分校間の往復で男女共に行われた。当時は車も少なく貸し切りロードレースになって、みんなよく走った。 ・そのうち小田急線が片平の山の買収をはじめ |
た。聞く所によると電車の線路をつけるとの事。あんな山の中をと思ったが、今になって驚いている。勿論、新百合ヶ丘駅の無かった頃の事。 ・プールが無かったので、夏休みは生徒と寺家ぜきに泳ぎに行った。水は豊富だったが少々濁っていたが、唯一の遊び場所だった。 ・農繁期休暇が一週間位あった。田植えで忙しい折学校を休んで、農家の生徒は家の手伝い、農家でない生徒は託児所で小さい子供の面倒を見ていた。 ・当時は柿生駅は線路の上を渡って反対ホームへ行く駅で一時間に二本位電車が通っていた。 ・その頃は卒業生は「金の卵」と言われる頃で、卒業生のほとんどが就職で進学する生徒はわずかであった。だから先生が生徒と一緒に各事業所を廻り雇ってもらうように交渉して歩いた。一日半歩いて無いときはがっかりして多摩川の土手で持って来た弁当を風に吹かれ乍ら食べたことを思い出す。とてもつらかった。 ・先生の卒業生に対するサインはいつでも「よいお嫁さんになって下さい」だった。卒業生の皆さんの幸せを願いつつ書いたものだった。 筆の進むままに十七年間の想い出をつづってみました。まだまだ多くあると思いますが、御判読下さい。 文中には記憶にある皆さんもおられる事と思いますが、なつかしい事ばかり。 皆様方の御健康と御幸せを祈りあわせて柿生中学校の御発展を祈念して終わります。山口県方面においでの折はぜひ立寄って下さい。 住所 〒758─0213 山口県阿武郡福栄村黒川503 |
| 同窓生レター① 仁ノ平 洋子 (12期) 森田先生が上京なされる事で、近隣在住の人達だけでもと、連絡を取り開かれた同級会でした。場所もなく、私どもの「ギャラリー喫茶・里山」を御利用戴き、卒業以来途切れていた思い出が次々と浮かび、話が終わる事がない、そんな会でした。先生も何十年もの空白を思い出すのに大変そうなご様子でした。 近況報告を含め夜中までの集まりで仲間が多方面で活躍されているのを知り、自分の事のように嬉しく、こうして集まりが出来るのも、それぞれの陰の奉仕があればこそと、改めて思いました。あの頃の柿中は木造校舎と渡り廊下、今思うと夢の様な風景でした。校舎から望む景色と校庭や教室、出席者は皆、懐かしく四十年前を思い出していた事でしょう。 |
|
| 同窓生レター② 中山 栄一 (24期) 昨年の十一月一三日、私達二四期の同窓会を八十余名の出席者で開催致しました。中学校を卒業して以来、実に二十八年ぶりの再会という人も何名かいて、面影の残っている人、すっかり変わってしまった人と、「驚き」と「懐かしさ」で楽しい時間を過ごしました。  恩師の先生方も、残念ながら渡辺先生は、所用で欠席でしたが、馬場先生、岸田先生、笹川先生に出席していただき、より一層盛り上がり、思い出話に花を咲かせ、またの開催を決定し、二次会、三次会と続いた同窓会は、散会となりました。 24期同窓会(271KB) |
|
再始動 星野 信之 創立五十周年を前に冷えきった同窓会のエンジンを動かすには、それなりの手順と整備が必要だった。 柿生式同窓会型エンジンと車体の構造を熟知している人々の協力により、平成八年六月、小清水新会長を中心に再始動を始めた。 規約も改訂され、同窓会入会式の運営や会報の発行と活発な動きが見られ、平成九年十一月の創立五十周年記念事業への協力や参加を機に、内外に同窓会再生を宣言した。 |
会報の発行も第三号になり、各期の情報や母校の近況など知るコミュニケーションの場として定着しつつあります。まだまだ課題も多いことと思いますが、年式二十二年のエンジンを冷やすことなく、着実に前進されることを願っております。 この間、多くの人々に話を聞いているうちに、私自身、同窓会の一員のような錯覚になってしまいました。心から同窓会の発展を願い、思い出の筆を置くことにします。 |
|
柿生中学校に赴任して 間中 禎二(22期) 前任校での勤務が十年をこえたため、他校への移動を希望していた私は、早くから移動の希望を出し、学校長からの移動の話を待っていました。 一月が過ぎ、三月になろうとしていたある日、体育館で卒業式の練習を指示していた私に、突然学校長が呼んでいるという連絡が来ました。 今さら、移動でもないだろうと思っていた私の耳 |
に、何と「柿生中に転任しないか?」という学校長の言葉が飛び込んできました。それも「今、この場で返事をしろ」との言葉に私の頭の中は真っ白になっていました。そして、私の口をついて出た言葉は、「はい、お願いします」でした。 あれから二年、今年は学年主任として、後輩である子供達の指導に当たっています。先輩、同級生、後輩の子供達もいたりして毎日、楽しい日々を過ごしています。 |
| 平成12年度 JOCジュニアオリンピックカップ 第19回全日本ジュニアバドミントン選手権大会に神奈川代表として二年生の清水寛子さんと保屋野慎司君が出場します。 ご活躍をお祈り致します。 |
| 事務局より 同窓会活動に協力頂ける方いらっしゃいましたら事務局までご連絡下さい。 ※同期会を開催する場合は、事務局までご一報ください。 |