桃生郡北村・伊東利蔵重村の次子で名を茂孝と称します。
4代藩主綱村公が幼くして藩主となるも、一関城主で曽叔父にあたる伊達兵部宗勝が宗家にならんものと画策したことを憂い、同門の采女重門と謀り之れを阻止しようとしましたが、この計画が発覚して捕えられ寛文8年4月28日、誓願寺河原(旧愛宕橋下)で処刑されました。享年36歳。
昭和12年宗家への孝心を顕影し建立したものです。
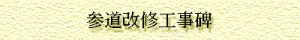
大正12年、吉田つぎ刀自は石段の荒れていることを憂い、嗣子・二郎大人と共に石段の補修と拝殿までの敷石200余間(約364m)を奉納いたしました。その工事は二郎大人が陣頭指揮にあたり、監督に当たっております。現在のように機械力はありませんので当時は全て人力です。急な参道の石段を補修することは並大抵の労働力ではありませんでした。この工事の費用一切は吉田つぎ刀自が奉納した篤信家です。
この誠意を後世に伝えるべく当時の力石雄一郎知事が篆額、竹駒神社大宮宗司社司之を撰文して、黄金山神社佐々木舜永社司が墨書し碑文としたものです。